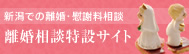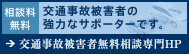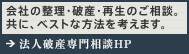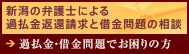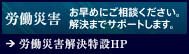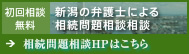最新情報
事務所からの最新情報や法律に関する情報をご紹介します。
特別受益とは?|特別受益の対象|持ち戻し期間と計算方法
2023年5月1日
コラム
目次
特別受益とは
特別受益の目的と背景
特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり生前に贈与を受けたりした者がいる場合、相続の際にその受けた利益を相続財産に加算して(=持ち戻して)相続分を計算するという制度です。
相続人の中で一部の者だけ被相続人から生前贈与や遺贈を受けたにもかかわらず、他の相続人と同様に相続分を受けられるとなると不公平が生じます。
そこで、このような特別受益は言わば相続分の前渡しに当たると見て、相続の際の不公平を解消しようとするのが特別利益という制度の目的です。
特別受益の対象となるもの
遺贈
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を無償で相続人や第三者(受遺者)に譲渡することです。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは、相続財産のうち個々の財産を遺言者が具体的に特定して遺言者が指定する人に遺贈するというものです。
対して、包括遺贈は、個別の財産ではなく、相続財産の全部又は一定の割合分を遺贈するというものです。
相続人に対する遺贈は、特別受益であっても包括受益であっても、その目的に関わらず特別受益の対象となります。
生前贈与
文字どおり被相続人が生前に相続人の一部の者に対し自分の財産を贈与していた場合ですが、生前贈与が特別受益に当たるかについては、贈与の目的や性質から見て相続財産の前渡しと評価できるか否かによって変わってきます。
民法上挙げられているのは、「婚姻若しくは養子縁組のため」あるいは「生計の資本」として贈与を受けた場合です。
婚姻・養子縁組のための費用
かつては婚姻の際に嫁入り・婿入りする側の実家が持参金や支度金と呼ばれる金員を用意するという慣習が広く行われていたようですが、これらは特別受益に当たるとするのが一般的です(他方、嫁や婿を迎える側が用意する結納金については解釈が分かれているようです)。
現代でも、結婚式や披露宴の費用を親に負担してもらったというケースはよくあると思います。
これらの費用負担については、親自身の親戚付き合いや社交儀礼上の支出という側面も強く、一概に相続財産の前渡しとまでは言い切れません。
したがって、特別受益には当たらないと解されています。
生計の資本
居住用不動産の贈与やその取得費用の贈与(家を建ててもらった)や営業資金の贈与(自営で事業を始めるに当たって資金を援助してもらった)などが代表的なケースです。
これらは子が親から離れて社会的・経済的に独立して生活を営むために必要な資金であることから、親の相続財産の前渡しと見ることが可能です。
したがって、特別受益の対象になるとされています。
他方で、新築祝いや出産祝いなどのいわゆるご祝儀は、親が通常行う援助の範囲内の金額にとどまる限りは、特別受益にはならないとされています。
また、遊興のための金銭の贈与も、生計を立てるのに必要な資本とは言えないことから、特別受益の対象とはなりません。

学費
義務教育終了後の高校、あるいは大学や専門学校の学費(授業料)ですが、これらは子の学力や資質に応じて親が負担すべき扶養義務の履行としての出費と考えられることから、よほど高額なものでない限り、特別出費には当たらないと考えられています。
とりわけ、相続人全員が大学等に進学して等しく高等教育を受け、ほぼ同程度の学費の援助を受けていた場合などは、相続人間に格別の不公平はないことから、特別受益性は否定されやすいでしょう。
死因贈与
死因贈与とは、死亡を条件に特定の人に財産を贈与する契約です。
相続人が被相続人から死因贈与を受けた場合は、特別受益に当たります。
特別受益の対象とならないもの
挙式費用や学費が特別受益の対象にならないのは上記のとおりですが、他にも以下のような受益は特別受益には該当しないと解されています。
生命保険
相続人のうちの一人が、被相続人の契約していた生命保険の死亡保険金の受取人として指定されているケースはしばしばありますが、死亡保険金の請求権は受取人と指定された相続人の固有の権利と考えられているので、原則として特別受益には当たりません。
しかし、判例では、死亡保険金の受取人となる相続人と他の相続人の間の不公平が「民法903条(特別受益の制度)の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、死亡保険金も特別受益に準じて持ち戻しの対象になるとされています。
死亡保険金は生命保険料を負担することによってはじめて支払われるものですが、その保険料は元々生前の被相続人の財産から拠出されたものです。
そうであれば、死亡保険金を受け取ることのできる相続人とそうでない相続人との間の格差が極端となり、相続人間の公平を図るという特別受益の制度の目的に反するような場合には、特別受益に準じた扱いをすべきだということになります。
具体的に死亡保険金が特別受益の対象になるか否かは、相続開始時点での相続財産の総額と、支払われる死亡保険金の総額の比率によって決まります。
端的に言うと、相続財産が極めて些少であるにもかかわらず、一部の相続人のみが高額な死亡保険金を受け取ったというような場合には、死亡保険金が特別受益の対象とされやすくなるでしょう。
死亡退職金
死亡退職金その他の遺族に対する給付は、遺族の生活保障を目的として支給されるものです。
そのため、特別受益に当たるとして持ち戻しを認めてしまうと、遺族の生活保障という制度趣旨を損なうおそれがあります。
したがって、特別受益には当たらないと考えられています。
被相続人の建物に無償で居住していた場合
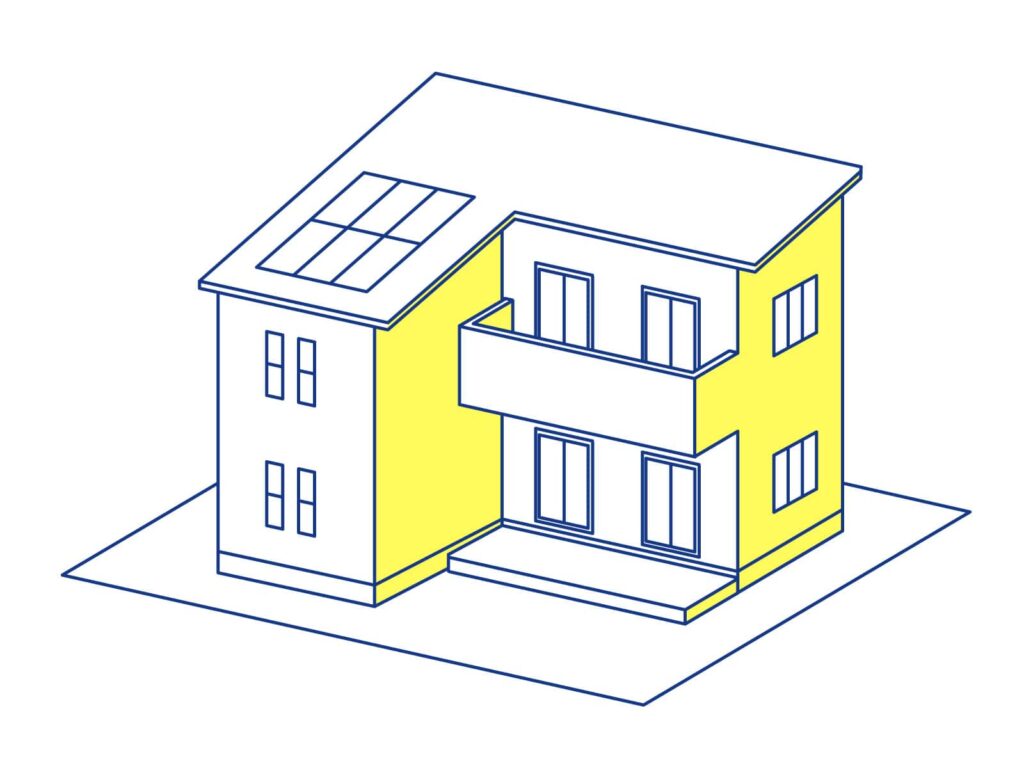
相続人の一人が、被相続人の所有する建物に無償で居住していたという場合、賃料に相当する額が特別受益に当たるかという問題が生じますが、結論としては当たらないケースが多いと考えられます。
まず、被相続人と相続人が同居していたというケースでは、相続人の立場はいわゆる占有補助者にすぎず、独立した占有権限を有するわけではありません。
そうすると、被相続人との間に使用貸借関係はないと評価できます。
また、とりわけ被相続人が高齢の場合、相続人の一人が介護や生活の支援のために同居を要請されることも多いと思われます。
このような場合、相続人がことさらに利益を得ていたとはいえず相続財産の前渡しとまでは言えないことから、特別受益には当たらないと考えられます。
また、相続人が被相続人と同居しておらず、独立の使用借権が成立していると見うる場合であっても、通常は被相続人から相続人に対する恩恵あるいは情誼により相続人に無償で居住することを認めていることが一般的と考えられます。
したがって、同居していない場合であっても、特別受益に当たらないことが多いと考えられます(ただし、本来他人に貸すべき収益物件に無償で居住していた場合など例外となるケースもあると考えられています)。
特別受益がある場合の持戻し期間について
特別受益の持戻し期間が10年へ改正
平成30年の民法改正に伴い遺留分制度に関する規定も改正されましたが、遺留分を計算する際の特別受益の持ち戻し期間が10年以内に限定されるようになりました。
具体的には、相続人の1人に対してなされた贈与のうち、特別受益に該当するものについては、相続開始前10年間になされたものに限り遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。
なお、10年の期間制限があるのは遺留分の計算に関する場合のみで、遺産分割協議の際の特別受益については、持戻し期間の制限はありません。
したがって、相続開始後10年よりさらに古い特別受益についても持戻しを主張できます。
配偶者への持戻し免除の改正
被相続人は、生前に特別受益を持ち戻さなくてもよいと意思表示をすることができます。
これを持戻しの免除と言います。
今般の民法改正により、夫婦間の相続において持戻し免除の推定規定が設けられました。
すなわち、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、被相続人に特別受益の持戻しの免除の意思表示があったもの推定されます(「推定」なので、被相続人が反対の意思表示(=持戻しを免除しないとの意思表示)をしていた場合には、本規定は適用されません)。
婚姻期間の長い夫婦において、配偶者に先立たれた他方の配偶者の老後の生活保障を図る趣旨です。
ここで言う「婚姻期間が20年以上」の意味ですが、相続開始時に20年以上の婚姻期間があるということではなく、居住用不動産を遺贈又は贈与した時点で婚姻期間が20年以上になっていることが必要です。
また、「婚姻」とは法律上の夫婦関係に限定され、事実婚は含みません。
対象となる不動産の「居住用」という要件は、遺贈又は贈与の時点で具備する必要があると解されています。
持戻しの計算方法
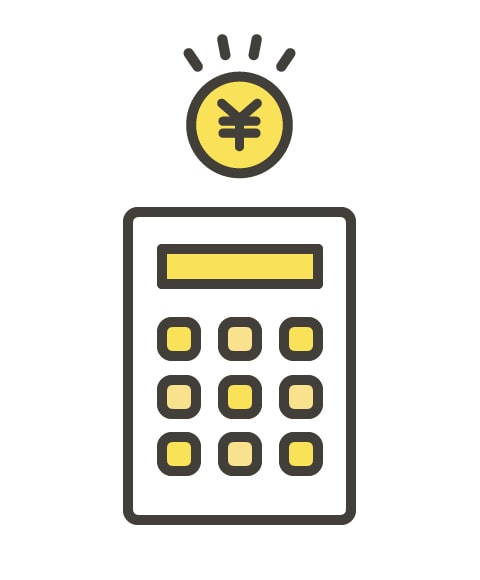
被相続人が甲で、相続人が甲の妻A、甲とAの間の長男B、二男C、長女Dと4名というケースで説明します。
相続開始時の甲の遺産が4500万円あり、また甲は生前長男Bが独立開業するに当たっての資金として1000万円を、長女Dには結婚の際の持参金として500万円を各人に贈与しており、かつ二男Cには遺言で1000万円を遺贈したとします。
まず相続開始時の被相続人の遺産に、相続人が受けた特別受益に当たる贈与の価額を加算して「みなし相続財産」を確定させます(なお、相続人が受けた遺贈の価額は加算する必要はありません。これは、遺贈は被相続人の相続開始時の遺産から支払われるものであり、加算すると遺贈の価額を二重で計算していることになるからです)。
上記の例で言うと、
4500万円(相続開始時の甲の遺産)+1000万円(Bへの開業資金の生前贈与)+500万円(Dへの持参金の生前贈与) =6000万円
がみなし相続財産となります。
次に、このみなし財産に各相続人の相続分を乗じて「一応の相続分」を算出します。
上記の例では、
妻A:3000万円(2分の1)
長男B、二男C、長女D:1000万円(各6分の1)
となります。
そして、この一応の相続分から特別受益の額を控除することで具体的相続分を算定します。
妻A:3000万円
長男B:1000万円-1000万円=0円
→具体的相続分は0円となりますが、開業資金1000万円の生前贈与が甲の相続財産の前渡しと評価されるため不公平ではないと考えられます。
二男C:1000万円-1000万円=0円
→具体的相続分は0円となりますが、これとは別に遺贈で1000万円を受けられます。
長女D:1000万円-500万円=500万円
特別受益を主張する場合
特別受益を主張する場合の流れですが、まず遺贈については遺言があることから明らかです。
問題は生前贈与の場合です。
不動産の贈与であれば、登記を確認すれば贈与の事実自体はすぐに把握できますし、使用状況からその目的を推認することは比較的容易でしょう。
他方、金銭の贈与については、贈与契約書や受取証などの客観的証拠がない場合には、被相続人の預貯金口座の取引履歴を取り寄せたうえで特別受益に該当すると思われる取引を地道に洗い出していくという作業を経なければならないケースが多いです。仮にお金の流れが把握できても、特別受益に該当することを立証するのは決して容易ではありません。
逆に、特別受益を主張された側としては、贈与の目的や性質について可能な限り客観的資料を示しつつ丁寧に説明していく必要があるでしょう。
まとめ
以上が特別受益の概要ですが、特別受益に該当するかどうかや特別受益がある場合の相続分の計算方法については法律や判例に関する知識が不可欠となります。
話し合いでの解決が難しい場合には家庭裁判所での調停や審判に進むケースも多いので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
▼▼合わせて読みたい▼▼