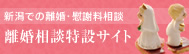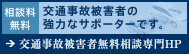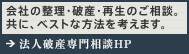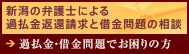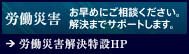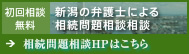最新情報
事務所からの最新情報や法律に関する情報をご紹介します。
遺産分割協議の概要と注意点
2023年3月31日
コラム
遺産分割協議とは
遺産分割協議の概要
遺産分割協議とは、亡くなられた方(「被相続人」と言います。)の財産(遺産)を相続人の間で分割するための話し合いのことです。
民法には、相続人と被相続人の身分関係に応じて法定相続分の規定がありますが、個々の遺産を具体的に誰が取得するかについての定めはありません。
あくまでも相続人間の話し合いによって決めることとされているので、遺産分割協議が必要となるのです。
なお、ここで言う遺産には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産等)のみならず、マイナスの財産(負債)も含みます。
遺産分割協議を行うタイミング
遺産分割協議は、相続開始後いつでも行うことができ、被相続人が遺言により5年を超えない範囲で遺産分割を禁止した場合(民法908条)を除き、法律上の制限はありません。
私がこれまで相談を受けた案件では、四十九日の法要が終わってから話し合おうという方がしばしば見受けられますが、これはあくまでご遺族の心情を踏まえた一般的な傾向にすぎません。
法律家の視点からは、遅滞なく遺産分割協議を行うのが望ましいと言えるでしょう。
なお、税務上は、相続税の申告期限である相続開始から10か月以内に遺産分割協議を成立させるのが理想的ですが、間に合わない場合は未分割のまま仮に相続税の申告を行い、遺産分割協議が成立した後で修正申告を行うことになります。
遺産分割協議が整わないという理由で相続税の申告期限が延びることはないので注意が必要です。
遺産分割協議を行わない場合のリスク
遺産分割協議を行わず放置しておくリスクとしてまず挙げられるのは、代を重ねるごとに当事者が増えて、実際に遺産を分割する必要が生じた場合に、協議を行うのが困難になってしまうという点です。
当初の相続(一次相続)について遺産分割協議をしないまま、一次相続の相続人が亡くなると、そこでさらに相続が発生することになります(二次相続)。
この場合、一次相続の相続分がさらに二次相続の相続人に相続される結果、相続の当事者が増えることになります。
このような場合、一次相続の遺産分割を行うには、一次相続人の地位を相続した二次相続人をも協議の相手としなければなりません。
兄弟姉妹であれば相互に交流があって連絡が取れるかもしれませんが、その下のいとこの世代、あるいはさらに下のはとこの世代となると、遠方にお住まいで中には今までに一度も会ったことがないという相続人が現れることもしばしばあり、遺産分割協議を円滑に行う上で支障をきたすおそれがあります。
また、預貯金については、先年最高裁判所が判例を変更し遺産分割協議の対象になるとの判断が示されました(最高裁平成28年12月19日決定)が、遺産分割をしないまま10年以上放置すると休眠口座となり、払い戻しや解約の際に通常よりも手続が煩雑になるといったデメリットもあります。
遺産分割協議の進め方

以下は、遺産分割協議の一般的な流れです。
遺言の調査
遺言は、自分の所有する財産を死後にどう処分するかについての被相続人の意思表示です。
したがって、被相続人の遺言があればそれに従うのが原則です(ただし、実務上は相続人全員の合意により遺言と異なる内容の遺産分割も可能とされています)。
遺言にはいくつかの種類がありますが、一般に利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
後者は、公証人に遺言書を作成してもらい、かつその原本を公証役場で保管してもらうという方式の遺言です。
昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言は日本公証人連合会がデータベースで管理しているので、公証役場に申し込めば遺言の有無を調べることができます。
他方、前者の自筆証書遺言については、従来は相続人が自力で探すしか方法がなかったのですが、令和2年7月から法務局が自筆証書遺言書を保管する制度が始まりました。
被相続人が生前この制度を利用していた場合には、法務局に照会すれば遺言の有無が分かります。
なお、自筆証書遺言では家庭裁判所での検認手続を経なければなりませんが、この保管制度を利用した場合には検認は不要とされています。
相続人の調査
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
したがって、誰が相続人なのかを確定することが必要になります。
通常は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せて配偶者や子の有無を調べます。
配偶者や子がいない場合には、父母や兄弟姉妹といった次順位の相続人についても順次戸籍謄本を取り寄せて相続人の範囲を確定させる必要があります。
なお、相続には同時存在の原則というルールがあり、相続開始時点で生存している方でなければ相続人にはなれません。
ただし、既に死亡している相続人に子や孫がいる場合には一定の範囲で相続が認められています(代襲相続)。
代襲相続は、既に死亡している相続人が兄弟姉妹の場合はその子(甥、姪)まで、直系卑属(子や孫)の場合は限定なく認められます。
相続財産の調査
他方、遺産分割の対象となる財産の範囲についても特定が必要になります。
現金はもちろん、預貯金や有価証券については、まずは被相続人の持ち物(通帳やカード)や被相続人宛ての郵便物を手掛かりに調べていくことになります。
金融機関や証券会社を特定できれば、取引履歴や相続開始時の残高証明書を取り寄せることで遺産となる金額を把握することができます。
不動産については、市町村ごとに所有不動産の一覧表(いわゆる名寄帳)が作成されていますので、まずは被相続人が生前居住されていた市町村から名寄帳を取り寄せることで不動産の有無を調べることができます。
負債についても、被相続人の持ち物(カード類)や郵便物(請求書など)から調べることになりますが、それでも明らかでないという場合には信用情報機関に照会する方法があります。
国内の金融機関や消費者金融、カード会社であれば、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)または株式会社CICのいずれかの信用情報機関に加盟していますので、これらの信用情報機関に照会をすれば負債の有無は判明します。
ただし、個人間での貸し借りはこれらの信用情報機関に登録されないので注意が必要です。
遺産分割の話し合い
遺産分割の当事者である相続人と、分割の対象となる遺産の範囲が確定すれば、いよいよ遺産分割の話し合いに入ります。
実務的に問題になりうるのは、相続人の中に被相続人から生前贈与を受けていたなど特別受益があるケースや、逆に被相続人の家業を手伝ったとか介護をしていたといった寄与分の主張があるケースです。
特別受益の範囲や、寄与分の類型についてはいくつかの論点がありますが、詳細は別稿で説明します。
今、特別受益や寄与分がある場合の具体的な相続分の計算方法について簡略化して説明すると以下のようになります。
①現金・預貯金・不動産といったプラスの財産から負債などマイナスの財産を引いて分割の対象となる相続財産を確定する。
②①の相続財産に特別受益を足し、さらに寄与分を引く(これを「みなし相続財産」と言います)。
③「みなし相続財産」に基づいて、各自の法定相続分を算定する(これを「一応の相続分」といいます)。
④特別受益を受けた相続人は、「一応の相続分」から特別受益を引く。寄与分がある相続人は、「一応の相続分」に寄与分を足す。 特別受益も寄与分もない相続人は、「一応の相続分」がそのまま具体的な相続分となる。
なお、すべての、または一部の遺産を特定の相続人が単独で取得する代わりに、他の相続人に対しては相続分に応じた代償金を支払うという遺産分割の方法もあります(代償分割)。
代償分割は、遺産を分散させたくない事情がある場合に用いられることが多い分割方法です。
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立すると、その内容を書面に残します。
形式に法律上の決まりはありませんが、通常は遺産目録を添付するなどして遺産の範囲を明確にさせることは必須です。
預貯金については、金融機関・支店、種別、口座番号、口座名義によって特定します。
このとき、敢えて残高を記載しないことが一般的です。
相続開始後も口座の凍結前に公共料金の引き落としがあったり、利息が発生していたりすることがあるため、相続開始時の残高と現在の残高が一致しないことがしばしばあるからです(全国銀行協会のホームページにも、預金残高に変動がある場合には、遺産分割協議書があっても改めて相続人全員の同意・承諾が必要になる場合もあると注意喚起されています)。
不動産については、必ず登記事項証明書を確認し、登記の記載どおり正確に記載します(そうでないと、遺産分割後に法務局で所有権移転登記を申請する際に支障が生じかねません)。
未登記建物については、上述の名寄帳の記載を手掛かりにして特定することになります。
遺産分割協議書の内容が確定すると、相続人全員が署名・押印します。
押印は認め印でも有効ですが、金融機関から預貯金の払い戻しを受ける際には普通実印での押印と印鑑登録証明書の添付を求められますので、実印を押すのが確実でしょう。
遺産分割協議書の形式としては、公証役場に行って公正証書を作成するケースもあります。
典型的なのは代償分割の場合です。
代償分割は、全部または一部の遺産を特定の相続人が相続する代わりに他の相続人に代償金を支払うというものですが、約束を反故にされて代償金が支払われないという事態もないわけではありません。
万が一の場合に備えて、約束を履行しない相続人の財産に対して強制執行することができるようにしておく必要があります。
そこで、遺産分割協議書を公正証書にすることによって、公正証書を債務名義とする強制執行が可能になるのです(なお、強制執行を可能にするには公正証書に「強制執行認諾文言」が付いている必要があります)。
遺産分割協議の実行
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書が完成すれば、その内容を実行に移します。
預貯金については、遺産分割協議書と必要書類を金融機関の窓口に持参して払い戻しを受けます。
このとき、相続人の中で代表者を決めたうえでその代表者が払い戻しを受け他の相続人に現金で分配するという方法と、各預貯金口座について個々に取得する相続人を決めたうえで各自払い戻しを受けるという方法があります。
いずれにしても金融機関ごとに求められる書類も異なってきますので金融機関への事前確認は必須です。
株式については、上場会社の株式であれば、その株式を取り扱っている証券会社に対して必要な手続を行えば名義の書き換えは完了します。
他方、非上場会社の株式の場合は、その株式を発行している会社に直接問い合わせて名義を書き換えてもらうことになります。
不動産については、法務局に遺産分割協議書その他の必要書類を持参して所有権移転の登記申請を行います。
本人のみで登記申請手続を行うのが難しい場合には司法書士に依頼するのが一般的です。
なお、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されます。
これによると、相続により(遺言も含む。)不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、また、遺産分割協議により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた登記の申請をしなければならないことになりました。
いずれの場合も正当な理由がないにもかかわらず放置した場合には、10万円以下の過料が科されることがあるので注意が必要です。
相続税については、納付期限(相続開始から10か月以内)前に遺産分割協議が成立していれば、その内容に沿って相続税の申告をします。
他方、納付期限までに遺産分割協議が成立せず、いったん法定相続分に基づいた申告をした後で、遺産分割協議が成立したというケースで実際に取得した遺産の額が申告した額と異なる場合には、修正申告または更正の請求をすることができます。
遺産分割協議がまとまらなかった場合の対処法
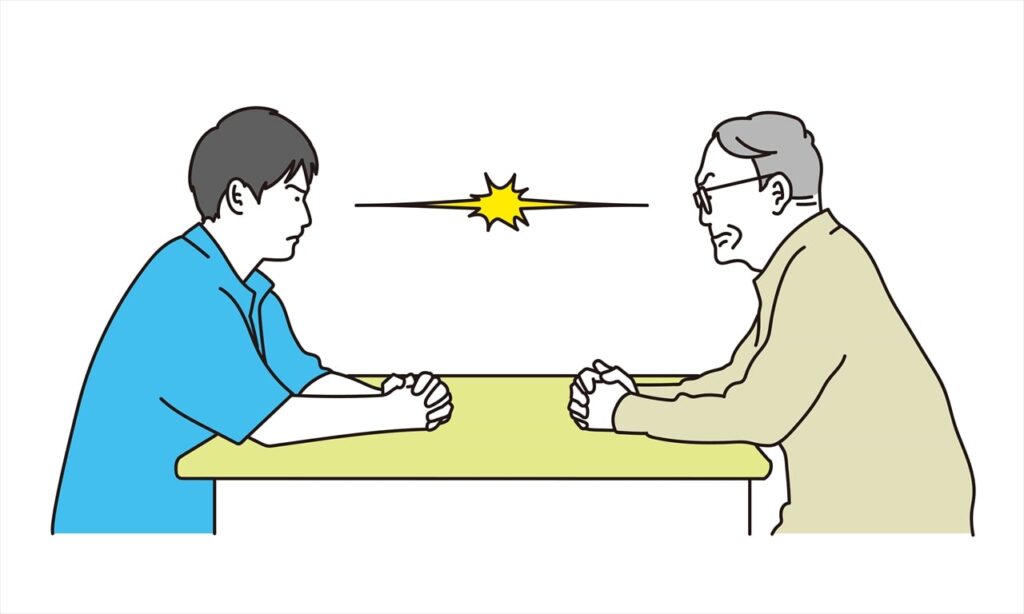
遺産分割は当事者の話し合いにより決めるのが原則であり、実際ほとんどのケースでは円満に解決しているものと思われます。
もっとも、「泣く泣くも良い方を取る形見分け」という古川柳のとおり、普段から険悪な関係にある相続人同士はもちろん、日ごろを仲良くしている相続人であっても遺産の内容が明らかになるや途端に話し合いが円滑に進まなくなる場合があることもまた事実です。
そのような場合は、以下のような方法を取ることが考えられます。
弁護士に依頼する
当事者同士で話し合いにならないという場合には弁護士を代理人に選任して協議することが一般的です。
とりわけ当事者双方に弁護士が就いた場合には、法律的な観点から争点を整理して着地点を見出すことができるので、協議が成立する見込みは高まるでしょう。
しかし、弁護士はあくまでも片方の当事者の代理人であって、中立の第三者的な立場にあるわけではありません。
そのため、当事者本人がどうしても納得できないという場合には、次に紹介する遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停
当事者間で協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
調停の流れは、家庭裁判所に遺産目録とともに調停申立書を提出し、指定された期日に出頭したうえで調停委員に対し交互に事情を説明し、解決を目指すというものです。
調停を主宰する調停委員会は、裁判官と調停委員2名(家事事件では男女各1名ずつ)で構成されます。
通常は、1か月に1回程度のペースで期日が開かれ、所要時間は1期日につき概ね2時間~3時間です(交互に話を聞かれるので、その半分は待ち時間と思ってください)。
当事者同士が顔を合わせる場面は普通ありません。
調停は、どちらの当事者の言い分が正しいかを決める場ではなく、あくまでも調停委員を交えた話し合いを通じて解決策を考える場です。
したがって、当事者の互譲(互いに譲歩すること)が不可欠なのですが、実務上ほとんどの事案は調停で解決することが多いように思います。
遺産分割審判
調停でも遺産分割協議が解決しない場合には、自動的に審判に移行します。
なお、遺産分割事件には審判に先立って調停を申し立てなければならないという原則(調停前置主義)が適用されないので、最初から調停を飛ばして審判を申し立てることも可能です。
しかし、ほとんどの場合は裁判所の職権で調停に付されます。
裁判所としても、話し合いによる解決の方が望ましいと考えているからでしょう。
遺産分割の審判は、当事者の主張や提出した資料をもとに裁判官が最終的な判断を法律的な観点から下すというものです。
したがって、必ずしも当事者の意向が反映されるとは限られません。
場合によっては、「こんなことなら調停で互譲しておいた方がよかった」と思うような内容の審判が出ることすらあります。
審判内容に不服のある当事者は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に即時抗告をします。
即時抗告を受けた上級審(高等裁判所)は、原審判の内容が妥当でないと判断した場合には、原審判を取り消して自ら審判を行います。
他方、原審判が妥当であると判断した場合には、即時抗告を棄却します(即時抗告に形式的な不備があった場合には、「却下」という判断をすることもあります)。
なお、即時抗告審に対する不服申し立ての手続もあるにはあるのですが(特別抗告と許可公告)、非常に限られたケースでしか認められません。
このように遺産分割に関する紛争は最終的には審判で決着するのですが、審判での判断対象には制限がある点にも注意が必要です。
例えば、相続人の範囲や遺産の範囲(ある財産が遺産に当たるかどうか)に関する争いは遺産分割の審判の対象にはなりません。
また、実務上しばしば争いとなる使途不明金の問題についても審判の対象外とされています。
したがって、これらを解決するには別途民事訴訟を提起しなければなりません。
遺産分割協議の注意点

相続人に認知症の人がいる場合
遺産分割は財産権の処分に関わる法律行為です。
したがって、遺産分割協議を行うには行為能力が必要とされます。
相続人の中に、認知症などで判断能力が不十分な方(制限行為能力者)がいる場合には、その度合いに応じて成年後見人や保佐人、補助人を選任したうえで遺産分割協議を行う必要があります。
手続上は家庭裁判所での成年後見人等の選任が先行するので、遺産分割協議の成立までに時間を要することもしばしばあります。
未成年の相続人がいる場合
未成年者も制限行為能力者ですので、通常は法定代理人である親権者が法律行為を行います。
ただ、例えば、父親が死亡して、母親と未成年の子どもが相続人になる場合、法定代理人である母親と子どもの間で遺産を巡って潜在的には利害が対立する状況になります(いわゆる「パイの奪い合い」という状況です)。
このような場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行い、その特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行います。
未成年の相続人が複数いる場合には、各人ごとに特別代理人を選任します。
音信不通の相続人がいる場合
遺産分割は相続人全員でする必要があるので、相続人と連絡を取れない場合には手続が先に進みません。
このような場合、戸籍の附票を取り寄せるなどして所在調査を行うのが通常です。
どうしても相続人の居場所が分からず連絡が取れないという場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その者を交えて遺産分割協議を行うことになります。
また、長期間にわたって連絡が取れずそもそも生死すら不明という場合には失踪宣告の制度を利用できる場合もあります。
失踪宣告がなされると音信不通の相続人は法律上死亡したとみなされて相続が開始するので、失踪者の相続人が判明している場合にはその相続人と遺産分割協議をすることになります。
遺産分割後に隠し財産や債務が判明したら
このような場合でも既に行った遺産分割協議が無効になるわけではなく、新たに判明した財産について遺産分割協議を行えばよいということになります。
ただし、新たに判明した財産が予想以上に高額だったり、負債の額が多かったりした場合には、既に行った遺産分割協議の内容について不公平を感じるケースもないわけではありません。
そこで、このような場合には、改めて遺産分割協議を行わざるを得ないことになります。
遺産分割は法律行為なので、相続人全員の合意があればやり直すことは可能なのです。
実務上は、新たな遺産が出てきた場合に備えて、「遺産分割後に新たな遺産が判明した場合には何某が取得する」といった条項を設けることあります。
ただ、これだけですべての事態に対処できるわけではないという点は留意しておくべきでしょう。
遺産分割後に遺言が見つかったら
遺言と遺産分割協議とでは遺言が優先するのが原則ですが、相続人全員の合意がある場合には遺言と異なる遺産分割をすることもできるとされています。
したがって、相続人全員の合意があれば既に行った遺産分割協議を優先させることは可能です。
ただし、遺産分割協議に加わった相続人の一部が、「遺言の存在や内容を知っていればそのような遺産分割協議はしなかったはずだ」と錯誤を主張した場合にそれが認められれば、先行する遺産分割協議が無効になることもあります。
また、遺言により認知がされていた場合や遺言により相続人の廃除がなされていた場合には、本来遺産分割協議に加わるべき者が加わっていなかった、あるいは遺産分割協議に参加する資格のない者が参加していたことになるので、先行する遺産分割協議は無効となります。
さらに、遺言の中で遺言執行者が指定されているケースでは、遺言執行者の追認がない限り遺言が優先します。
遺言の内容が、相続人以外の第三者(受遺者)への遺贈を含むものであった場合も、受遺者の利益を無視することはできず遺言に沿って遺贈を実現しないといけません。
まとめ
以上、遺産分割協議について概観してきましたが、遺産がまったくないとか負債ばかりで相続放棄を検討しているといった場合でない限り遺産分割協議は不可欠であり、しかも適切な協議を行ううえで法的知見は必須と言えるでしょう。
遺産分割に直面した方は是非とも弁護士に相談されることをお勧めします。
▼▼合わせて読みたい▼▼